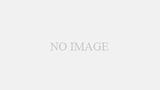2019年、ジョーダン・ピール監督が『ゲット・アウト』に続いて発表した『Us/アス』。
「自分たちにそっくりなもう一人」が家に現れるというシンプルなスリラー構造の裏に、分断・階級・記憶・国家の影が織り込まれた本作は、単なるホラーにとどまらない“現代アメリカの寓話”として話題を呼びました。
この記事では、制作秘話から演出意図、演技の技巧、視覚設計、そして考察の鍵を25のトリビアとして紐解いていきます。
🎬制作と構想にまつわるトリビア
01|“アメリカというホラー”が発想の出発点
ピール監督は「アメリカにとって最大の敵は、常に“自分たち自身”だ」と語っており、“Us=US(合衆国)”というダブルミーニングが初期からタイトルに織り込まれていました。
02|脚本執筆はわずか2ヶ月で完了
アイデアの蓄積は長年あったものの、実際の執筆期間は非常に短く、ピールは「これまでで最も直感的に書けた脚本」と述べています。構成はホラー+寓話+SF+ブラックコメディのハイブリッド。
03|『チャドの復讐』からの影響
監督は1986年公開のB級ホラー『チャド』(C.H.U.D.)に言及しており、“地下にいるもう一人”という構造が本作のヒントになっていると公言しています。
04|ロケ地は“分断”の象徴カリフォルニア
サンタクルーズの海岸が舞台に選ばれたのは、観光地の顔と貧困・ホームレス問題が同居する“二面性”のある土地だからです。撮影も実際に現地で行われました。
05|“ハンズ・アクロス・アメリカ”が物語の暗号に
1986年に実際に行われたチャリティ企画「ハンズ・アクロス・アメリカ」は、階級と社会正義をテーマとした象徴的イベント。本作ではこの象徴が“ズレた理想の再現”として機能します。
🧍キャストと演技にまつわるトリビア
06|ルピタ・ニョンゴは“二役”で全く異なる演技を披露
主演のルピタは、母親アデレードと、地下のレッドという二役を演じ分けました。レッドの演技には“気道損傷後の声”を参考にした声帯トレーニングが行われました。
07|子役たちも全員二役
双子のように登場するテザーズ(影の存在)たちは、全員が実在のキャラクターの“歪んだコピー”として設計されており、子役たちもその差異を演技で見せる訓練を積んでいます。
08|レッドのダンスは“記憶の断片”から構成
レッドの動きは、アデレードのダンス記憶が歪んだ形でコピーされている設定。振付師による緻密なシーケンス構成が行われ、狂気と美しさを同時に表現しています。
09|“笑いと恐怖の反転”を俳優たちが担当
本作では一見明るいシーンでも不穏な間が多用されており、俳優には“恐怖とユーモアの境界を操作する”演技指導が与えられました。
10|“地上の家族”と“地下の家族”は同じセットで撮影
上下関係を象徴するシーンは、同じ空間でカメラアングルと照明を変えることで演出されています。これは予算と演出意図の両面から導き出された方法でした。
🎥演出と構造に関するトリビア
11|色彩設計は“地上=暖色/地下=寒色”で対比
地下の世界は青みがかり、地上は暖かい色調に設定されており、“同一人物”でもまったく違う存在に見えるように設計されています。
12|ミラー構造のショットが多数
本作には鏡面反転のようなショットが多用されています。これは“自分自身の恐怖”を象徴すると同時に、構造的に“どちらが本物か”を曖昧にする仕掛けでもあります。
13|BGMは“流行歌の歪曲”で構成
主題歌「I Got 5 On It」は、オリジナルのヒップホップ曲をクラシック風に再構成。平和な楽曲が不穏に変化することで、“世界が裏返る”不安を演出します。
14|“影の自分”の衣装には“囚人服”の暗喩
赤いジャンプスーツは、集合的な囚人を思わせるコスチュームであり、“押し込められた者たち”としてのテザーズを視覚化しています。
15|はさみのモチーフ=“断絶と分裂”の象徴
殺人道具として使われるハサミは、同じ形をした左右が決して交わらない道具であり、“一対でありながら永遠に切り離された存在”を象徴しています。
🎞️映像・音楽・細部に込められた工夫
16|タイトルシークエンスのウサギは“繁殖”と“実験動物”の暗喩
冒頭に登場するウサギたちは、地下世界の犠牲・実験・循環を象徴しています。また、本作の“影の社会”がいかに人工的に作られたものかを暗示しています。
17|エレベーター=地上と地下をつなぐ“精神の昇降機”
地下世界への入口は、実は遊園地の“ミラー迷路”の裏手に隠されています。
この物理的なエレベーターは、記憶・トラウマ・社会階層のメタファーです。
18|“繰り返される手のつなぎ”演出
劇中では何度も“手をつなぐ”行為が繰り返されます。これは、連帯か恐怖かを常に問い直す演出装置として使われています。
19|“白人家族の死”がブラックジョークに
劇中で白人家族があっけなく殺されるシーンは、観客の予測を裏切ると同時に、“誰も特権的ではない”というテーマを風刺的に表現しています。
20|地上のアデレードが“本物ではない”伏線が随所に
ダンスをやめた理由、リズム感、言葉の抑制など、アデレードが実はレッドだったことを示す伏線が細かく張り巡らされています。
🔍テーマと解釈に関するトリビア
21|“分断国家アメリカ”の寓話
地上の人間たちは裕福で自由だが、地下の人々は閉じ込められ、言葉も持たない。これは貧困・人種差別・階級のメタファーです。
22|“誰かの幸せは誰かの犠牲の上にある”
アデレードが家族を築けたのは、誰かの人生を奪ったから。これは現代社会全体が構造的に抱える“不可視の搾取”を問いかける寓話です。
23|“声”の喪失は表現力の抑圧
地下の人々は言葉を奪われています。それは“声を持たない”こと=社会に存在しないことの象徴です。
24|“他者の痛みに目を向けるか”が試される物語
主人公たちは最後まで“地下の人々の苦しみ”に完全には共感できません。それは観客自身の共感力をも試す仕掛けです。
25|“私たち=Us”の意味が反転する
観終わった後、「Us(私たち)」とは誰を指していたのか? 地上か、地下か? その問いが観客に突き刺さる構造になっています。
📝まとめ
『アス』は、スリラーとしての緊張感と、現代社会における分断や抑圧を寓話的に描いた知的ホラーの傑作です。
「自分とそっくりな存在が、自分の居場所を奪いに来る」という恐怖は、他人ごとではなく、私たち自身の姿を映し出す鏡でもあります。
この25のトリビアを通じて、もう一度“自分の影”を見つめ直してみてください。