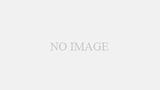2022年、異色のサスペンス映画として注目を集めた『ザ・メニュー』。
ラルフ・ファインズ演じるカリスマシェフと、アニャ・テイラー=ジョイ演じる謎めいた客が織りなす“食の地獄絵図”は、ジャンルの枠を超えた衝撃を観客に与えました。
この記事では、制作秘話からキャストの舞台裏、細部の演出、そして物語の深層に込められたテーマまで、25のトリビアを通して『ザ・メニュー』の真髄に迫ります。
🎬制作と構想にまつわるトリビア
01|脚本は“料理界の狂気”を風刺するアイデアから始まった
脚本家ウィル・トレイシーは、実際にノルウェーの孤島にある高級レストランを訪れた際の経験が本作の発端だと明かしています。食文化の異常な格式ばった空気に違和感を覚え、そこから“料理のカルト”という発想が生まれました。
02|アダム・マッケイが製作を担当
風刺作品の名手アダム・マッケイ(『バイス』『ドント・ルック・アップ』)がプロデュースを手がけたことで、サスペンスに社会風刺の要素が融合。料理界への痛烈な皮肉が随所に込められています。
03|初期構想では“コメディ寄り”だった
初期の脚本ではより風刺的かつコメディ色の強いトーンでしたが、監督マーク・マイロッドの手により、スリラーとしての緊張感を前面に出す方向に修正されました。
04|ロケ地はジョージア州の海岸近く
架空の孤島“ホーソーン島”は、実際にはアメリカ・ジョージア州のサバンナ沿岸にあるプライベートアイランドで撮影されました。隔絶された雰囲気がリアリティを加えています。
05|料理監修は本物のミシュランシェフ
映画内の料理は、ミシュランスターを獲得したシェフ、ドミニク・クレンが全面監修。視覚的な完成度とリアリズムを支える要となっています。
🧍キャストと演技にまつわるトリビア
06|ラルフ・ファインズの役作りは“宗教指導者”がモデル
ファインズはシェフ・スローヴィクを“カリスマ的な教祖”のように演じることを意識しており、実際のカルトリーダーの資料を研究したと語っています。
07|アニャ・テイラー=ジョイは唯一の“部外者”として描かれる
マルゴ役は他の客たちとは異なり“階級外”の存在。彼女が異物として物語に入り込むことで、観客と同じ視点を担うキャラクターとして機能します。
08|ニコラス・ホルトは“フーディー”の滑稽さを体現
彼の演じるタイラーは、知識だけを振りかざす“美食マニア”の滑稽さと危うさを象徴した存在。皮肉の効いたキャラクター造形が話題を呼びました。
09|演出の多くが“舞台演劇”的に設計されている
キャストは多くのシーンで“1カット長回し”の中で演技を求められ、緊張感のある舞台劇のような空気が保たれています。特にダイニングシーンはその傾向が顕著です。
10|監督は俳優の“内面の空腹感”に注目して演出
マイロッド監督は、役者たちに「自分のキャラクターが本当に何に飢えているのか」を考えさせたといいます。これは単なる空腹ではなく、承認欲求や成功欲といった“内なる渇き”を意味していました。
🎥演出と世界観のトリビア
11|店内のレイアウトは軍隊式に統一
厨房スタッフの動線や振る舞いは、まるで軍隊のように緻密に統制されています。この統制はシェフ・スローヴィクの支配的な思想を視覚的に表しています。
12|画面構成はミニマルかつ幾何学的
シンメトリーや直線構図を活用し、冷徹な美しさを追求した映像設計。建築的で抑制された空間が、逆に緊張感を高めています。
13|音楽は不協和音をあえて多用
コリン・ステットソンによるスコアは、美しさと不穏さのバランスを巧みに操っています。ミニマルな旋律に不安定なリズムを重ね、観客に持続的な不安を与えます。
14|料理のプレゼンも“パフォーマンス”の一環
作中で紹介される料理は、まるで現代アートのように演出され、スタッフの動きまで含めて“芸術作品”として設計されています。
15|“タイラーのタコス”は即興で生まれたシーン
“料理できない人間が料理を作る”という屈辱的な場面は、脚本の中でも後半に追加されたアイデア。ニコラス・ホルトの即興演技が印象的なシーンとなりました。
🎞️映像・音楽・細部に込められた工夫
16|コース名は実在レストランのメニュー風
各料理のタイトルやプレゼン方法は、実在のミシュランレストランで提供されるコースの様式を模倣しています。特に“解体料理”のシーンはその影響が色濃く出ています。
17|スタッフのコスチュームは“無個性”を意図
厨房スタッフの制服は、あえて無個性で画一的にデザインされています。これは集団主義とシェフの絶対的支配構造を象徴しています。
18|招待客の席順にも意味がある
客たちの配置は、社会的立場や物語的な“罰の順序”に従って構成されており、意図的に画面内の力関係を視覚化しています。
19|料理の撮影には“フードスタイリスト”が常駐
食品広告の撮影に携わるプロのフードスタイリストが現場に常駐し、料理がどの角度でも美しく映るよう徹底されていました。
20|スモアの火は本物
クライマックスで登場する“スモアの儀式”では、実際に火を用いた特殊効果が使われており、役者の安全にも細心の注意が払われました。
🔍テーマと解釈に関するトリビア
21|“消費文化”への批判が中心テーマ
『ザ・メニュー』は、金と名声のために文化を消費し尽くす現代人への強烈な風刺。観客は“美食”という名のもとに搾取される芸術の現場を目撃することになります。
22|“芸術家と観客”の関係を問う作品
シェフと客の関係は、芸術家とその受け手の比喩として描かれており、受け手の“無知と支配欲”が創作者を蝕んでいく構図が示されています。
23|“サービス業”の地獄を描いているとも読める
スタッフが命令に従い続ける姿や、料理人の限界を超えたサービス精神は、現代の“サービス過剰社会”を皮肉った構図としても成立します。
24|マルゴの存在が持つ“希望”
唯一“贈与”として料理を受け取ったマルゴの存在は、芸術が機能するには“心からの受容者”が必要だという示唆。だからこそ彼女は生き延びるのです。
25|スモアは“アメリカ的終末”の象徴
スモアという“子ども向けの甘味”で人々を焼き尽くすという構図は、消費社会が自己破壊を招くという強烈なアイロニー。最もシンプルで皮肉の効いたエンディングです。
📝まとめ
『ザ・メニュー』は、美食スリラーというジャンルを超えて、現代社会そのものを映し出す鏡のような作品です。
その演出や細部、演技のすべてに“批評性”と“創作論”が詰め込まれており、何度でも見返したくなる奥深さがあります。
これらのトリビアを手がかりに、ぜひ再びこの恐ろしくも美しいフルコースを味わってみてください。