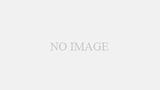2021年、アイスランドの大自然と異形の存在を題材に話題を呼んだA24配給の『ラム』。
人間と羊のあいだに生まれた“何か”を育てる夫婦の姿を描いた本作は、静謐な映像美と不穏な空気感で世界中の観客を魅了しました。
この記事では、その制作背景からキャストの秘話、演出のこだわり、象徴的なテーマ解釈まで、25のトリビアを通じて『ラム』の深層に迫ります。
🎬制作と構想にまつわるトリビア
01|監督は元VFXアーティストだった
ヴァルディミール・ヨハンソン監督は、もともと視覚効果アーティストとして活動しており、『ローグ・ワン』や『ゲーム・オブ・スローンズ』にも関わっていました。『ラム』は彼の長編初監督作ですが、映像美とVFXの融合が特に高く評価されています。
02|アイスランドの伝承が着想源
本作の発想源は、アイスランドに伝わる動物と人間が混ざり合う神話や昔話にあります。特に「ヒトの顔を持つ動物」や「妖精と子をなす」伝承が脚本に影響を与えています。
03|脚本はパートナーとの共同執筆
脚本は監督と詩人・作家であるショーン・共同で執筆。台詞は極力削ぎ落とされ、イメージと映像で語る構成が特徴です。
04|セリフの少なさが意図的に設定された
セリフの総量は非常に少なく、静寂と空気感を意識的に用いる演出が脚本段階から練られていました。言葉よりも自然音や視線が物語る世界観です。
05|自然との共生を撮るためにロケ地に長期滞在
主要な撮影はアイスランドの僻地で行われ、撮影クルーは自然との一体感を高めるため数週間現地で共同生活を送りました。家畜との親和性を高めるための手法でもありました。
🧍キャストと演技にまつわるトリビア
06|ノオミ・ラパスが製作にも参加
主演のノオミ・ラパスは女優だけでなくプロデューサーとしても本作に参加しています。アイスランド語を流暢に話せる彼女の存在が企画実現の鍵となりました。
07|アダを演じた子役は3人いた
羊と人間のハイブリッドである“アダ”のキャラクターは、VFXだけでなく3人の子役(1〜3歳)が実際に演技を担当しました。動きや仕草に「子どもらしさ」を加える工夫がされました。
08|ラパスが本物の羊の出産を見守った
撮影中、ノオミ・ラパスは実際の羊の出産シーンに立ち会い、命の誕生をリアルに感じることで役作りに活かしたと語っています。
09|羊との関係性を築くための訓練
キャストは撮影前に羊の世話や抱き方、接し方を学ぶ時間が設けられました。羊がストレスを感じず自然に振る舞うことが重要だったためです。
10|“アダ”の撮影に多層的アプローチ
“アダ”のシーンは子役・羊・VFXの3パターンを撮り分けて組み合わせる方式がとられ、撮影は通常の倍以上の手間がかかりました。
🐑異形の存在と静寂に満ちた演出トリビア
11|ジャンルは「牧歌的ホラー」と呼ばれる
本作は「ホラー」とカテゴライズされがちですが、暴力描写よりも不穏な空気や静かな狂気が主軸で、監督自身は“牧歌的ホラー”と呼んでいます。
12|1カットの長回しが不安を増幅
演出では1カットの長回しが多用され、観客に“見守るしかない”感覚を与える仕掛けとなっています。日常の中に潜む異常をあぶり出す技法です。
13|アダの存在は“自然の逸脱”の象徴
人間と動物の境界を超えた存在であるアダは、“人間の都合で自然を変えること”への警鐘を暗に表しており、演出にもその視点が貫かれています。
14|「母性」というテーマの描写を意識
演出の随所に“育むこと”と“支配すること”の差異が描かれており、ラパスの演技と演出の抑制された感情表現でその葛藤が浮き彫りになります。
15|ラストの構図は黙示録的象徴
終盤のアダを巡る運命と“角の生えた存在”の登場は、神話や宗教的イメージを彷彿とさせ、観客に“何かを裁かれた”印象を残します。
🎞️映像・音楽・細部に込められた工夫
16|“アダ”の合成にVFXの粋を結集
“アダ”の外見は子役の顔と羊の身体を3D合成で融合。リアルすぎない、絶妙な違和感を目指して何度も修正が重ねられました。
17|音楽は極力排除、自然音が支配
劇伴音楽は極端に抑えられ、風・雨・動物の声などが重要な“語り”の役目を担います。これにより観客の不安感が増幅されます。
18|アナモルフィックレンズによる圧迫感
映像はアナモルフィックレンズを使用し、左右に広がるが上下は狭い構図を作り出しました。この縛られた視界が、閉塞感と不安を生む効果に。
19|衣装と美術は極力“現地そのまま”
衣装や家のインテリアも、アイスランドの実際の生活感を再現。あえて飾らない生活が、非現実とのコントラストを際立たせます。
20|色彩は“寒冷トーン”で統一
全体の色彩はブルーグレーやくすんだ緑でまとめられ、温もりを排したことでアダの存在が逆に“生命の温かさ”として浮かび上がります。
🔍テーマと解釈に関するトリビア
21|“奪う愛”と“育む愛”の対比
物語全体は、失ったものを埋めようとする“奪う愛”と、あるがままを受け入れる“育む愛”との対比が主軸にあります。観客に“本当に正しい愛とは?”を問いかけます。
22|“自然への罪”を突きつける寓話
人間が自然から奪った命、干渉し続けたツケがアダの存在に象徴されており、本作全体が環境倫理の寓話として読むこともできます。
23|アダの存在=罪の結晶
アダという存在は愛らしい一方で、自然の理を曲げた“代償”そのものであり、倫理的に見ると「可愛さ=正義ではない」視点が現れます。
24|“復讐者”としての角の生えた存在
ラストに登場する角を持つ存在は、自然の“回収者”とも呼ぶべきキャラクターで、神や自然の意志を象徴しています。
25|“静寂”が意味するのは喪失
全編にわたる静けさは、ただの演出ではなく、“失われたもの”と向き合い続ける感情の余白として存在します。静寂は、言葉以上に多くを語っています。
📝まとめ
『ラム』は、異形の存在や神話的モチーフを借りながら、人間の愛と罪、そして自然との関係を鋭く描き出した一作です。
その静かな狂気と緻密な映像表現、そして多層的なテーマは、トリビアを知ることでさらに味わい深くなります。
あなたもぜひ、あの沈黙のなかに潜む“問い”をもう一度味わってみてください。