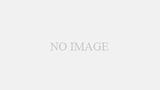2020年、コロナ禍に公開されながらも世界中に深い余韻を残し、アカデミー賞作品賞・監督賞・主演女優賞を受賞した『ノマドランド』。
アメリカの現代社会を生きる“移動民=ノマド”の姿を、静謐かつ詩的に描いた本作は、多くの人に“生き方”を問いかけました。
この記事では、その制作背景からキャスト、演出の哲学、映像と音響の緻密な設計、そしてテーマの解釈に至るまで、25のトリビアで『ノマドランド』の魅力に深く迫ります。
🎬制作と構想にまつわるトリビア
01|原作はノンフィクションルポだった
本作はジェシカ・ブルーダーのノンフィクション『ノマド: 漂流する高齢労働者たち』を原案としています。リーマン・ショック以降、アメリカで実際に増加した高齢の移動労働者の実態を取材した記録が、映画の骨格となりました。
02|クロエ・ジャオが脚本・編集も担当
監督のクロエ・ジャオは脚本・編集も手がけており、本作のほぼすべてのクリエイティブを一人で掌握しています。現地取材・映像設計・登場人物との信頼関係づくりなど、ドキュメンタリー的手法が強く反映されています。
03|パンデミック直前にギリギリで完成
撮影は2018年末から2019年にかけて行われましたが、編集作業は2020年春まで続きました。完成直後に世界はコロナ禍に突入し、映画祭の中止・延期が続く中でヴェネツィア国際映画祭の開催が決定。そこからアカデミー賞まで駆け上がる異例の展開を見せました。
04|製作会社はサーチライト・ピクチャーズ
ディズニー傘下のサーチライトが製作を担当していますが、映画の内容は資本主義の現実を厳しく描いています。この“矛盾”こそが本作の存在意義であり、大手スタジオでも社会派映画を成立させ得るという証明となりました。
05|撮影スケジュールはわずか4ヶ月
アメリカ西部各地を巡りながら、冬から春にかけて撮影は実施されました。移動しながらの撮影のため、天候や自然光に左右されやすく、柔軟なプランと即興的な現場対応が求められました。
🧍キャストと演技にまつわるトリビア
06|主演はフランシス・マクドーマンドの企画発案から
主演のフランシス・マクドーマンドが、原作の映画化権を取得し、自ら主演・製作を兼ねてクロエ・ジャオに監督を打診しました。つまりこの映画は、マクドーマンド自身の“信念のプロジェクト”でもあるのです。
07|実際のノマドが多数出演
劇中に登場する多くの“ノマド”は、実在の人物たちです。ボブ・ウェルズやリンダ・メイなどは、原作にも登場する本人で、彼らの語る言葉や暮らしは脚本ではなく本人の経験から発せられています。
08|フランシスは実際にバンで生活した
役作りのため、フランシス・マクドーマンドは実際に車中泊を行い、ノマドたちと共に生活しました。ゴミ処理や炊事、トイレの確保まで、自ら体験したことで演技にリアリティが宿っています。
09|全編ほぼノーメイクでの出演
フランシスはほぼノーメイクで出演し、老いや疲労、自然光による肌の変化などもそのまま写し出されます。これは“演技”を極力消すための工夫であり、ドキュメンタリーと劇映画の境界を曖昧にするための演出でもあります。
10|マクドーマンドと一般人の関係性に配慮
実在のノマドたちとの関係を築くために、フランシスは現場であえて“有名人”を装わず、名乗りも抑えて撮影に臨みました。この距離感が信頼を生み、自然なやり取りと撮影が可能になったのです。
🎥演出と世界観のトリビア
11|物語の舞台は“資本主義の裏側”
アメリカの祝祭的な風景を背景にしながら、その裏にある搾取や孤立が描かれています。アマゾンの倉庫や公営キャンプ場など、現実の構造が“物語”を必要とせずに語る世界観を構築しています。
12|ジャンルに属さない“ロード・メディテーション”
『ノマドランド』はロードムービーでありながら、従来の物語構造を拒否しています。事件もクライマックスもなく、ただ風景と心が移ろう。その静けさこそが、“瞑想映画”とも呼ばれる理由です。
13|建物の“外”で語る映画
主人公ファーンは、ほぼ全編を屋外で過ごします。室内や社会の枠からこぼれ落ちた者の“まなざし”として、風や光、空の広がりが内面を語っています。
14|カメラはドキュメンタリー的な接近
手持ちカメラによる近距離撮影が多く、俳優と観客の“間”を感じさせません。これはクロエ・ジャオがドキュメンタリー作品から学んだスタイルで、観客を“共に旅する仲間”の視点に置く狙いがあります。
15|“時間の流れ”を可視化する演出
日の出・月の出・雪解け・花の咲く順番など、映画には季節と時間の経過が繊細に織り込まれています。登場人物の感情の変化と自然のリズムが静かに呼応し、心の移ろいを可視化しています。
🎞️映像・音楽・細部に込められた工夫
16|音楽はルドヴィコ・エイナウディのピアノ曲
本作の劇伴には、イタリアの作曲家ルドヴィコ・エイナウディのピアノ曲が使用されています。繊細で感情に寄り添う旋律は、セリフよりも雄弁にファーンの心情を語り、風景と響き合うように構成されています。
17|自然光のみで撮影されたシーンが多い
多くのシーンが自然光のみで撮影されています。日の出の柔らかい光や曇天のグレー、夕暮れの赤など、現実の空がそのまま“照明”となり、ファーンの孤独や穏やかさを照らし出しています。
18|バンの中の撮影はすべてリアルセット
ファーンの暮らすバン内部の撮影は、実際の車内空間を使用。狭さや生活感がカメラに制限を与えることで、リアルな視点や圧迫感を演出しています。わざと不安定な画角を選ぶことで、観客にも居心地の悪さが伝わります。
19|衣装はすべて“自前”に見えるリアリティ
ファーンの衣装は、フランシス自身が普段着ているものに近いスタイルで構成されています。既製服・古着・着古された生地感など、キャラクターの経済状況と“旅の履歴”を語る重要な要素となっています。
20|音響デザインは“静けさ”が鍵
本作ではBGMよりも環境音が強調されています。風の音、虫の羽音、遠くの列車の音など、孤独な時間が音で伝わってくる設計。これにより、観客が“都市の騒がしさ”との対比で彼女の生活を体感できます。
🔍テーマと解釈に関するトリビア
21|“喪失”と“再構築”の物語
夫を亡くし、町を離れたファーンの旅は、“何かを見つける”のではなく、“失ったものと折り合いをつける”プロセスです。喪失と孤独は癒されるのではなく、“持ち歩く”ことで生き方に昇華されます。
22|“家”とは何かを問い直す
『ノマドランド』では、“家を持たない”ことが“ホームレス”ではなく、“ホームフル”であるという言葉が登場します。建物ではなく、記憶・感情・選択の中に“家”を見出すという価値観が全体を貫いています。
23|資本主義社会の限界を優しく突く
アマゾン倉庫で働く高齢者や、医療の行き届かない現実は、強烈な社会批判でありながら、演出では決して怒りを前面に出しません。静かな観察と寄り添いの姿勢が、むしろ深い問いを観客に残します。
24|旅の終わりは“帰る”ことではない
ファーンはラストで再び出発しますが、そこには絶望ではなく“選択”の意思があります。彼女は「どこにも属さない」ことで、自分自身の生き方を肯定したのです。映画は“さよなら”ではなく“またね”という言葉で幕を下ろします。
25|“他人の人生を見つめる”ことの意味
本作の真の主題は、ファーンの人生を通じて“あなたの人生はどうか”を問うことにあります。観客が“誰かの旅”を見つめることで、自分の現在地と未来の形に目を向ける――それが『ノマドランド』の本質です。
📝まとめ
『ノマドランド』は、静かで美しい映像に包まれながらも、私たちの価値観や社会構造を根底から揺さぶる力を持った作品です。
物語がないようでいて、すべてを物語っている。そんな映画の形を知ることで、観客自身が“旅の仲間”となっていきます。
25のトリビアを通して、その深さと丁寧さを知った上で観直せば、また新たな“道”が見えてくるかもしれません。あなたもぜひ、ファーンの旅路にもう一度寄り添ってみてください。