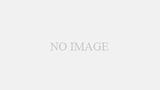2016年に公開され、第89回アカデミー賞で史上最多14部門ノミネートという快挙を成し遂げた『ラ・ラ・ランド』。
デイミアン・チャゼル監督が描く、夢を追う男女の出会いと別れを描いた本作は、美しい音楽と映像、切ないラストで世界中の観客を魅了しました。
この記事では、制作の舞台裏からキャストの秘密、演出のこだわり、音楽と映像に込められた工夫、そしてテーマに関する考察まで、全25のトリビアを通して『ラ・ラ・ランド』の魅力を徹底解剖していきます。
🎬制作と構想にまつわるトリビア
01|脚本は大学時代から温め続けていた
デイミアン・チャゼル監督は、大学在学中から『ラ・ラ・ランド』の構想を練っていました。ハリウッドの夢と現実を描くこの物語は、彼自身が映画業界を目指す中で感じた葛藤や希望が色濃く反映されたものです。実際、彼はこの脚本を先に書いていたものの、実現の難しさから一度保留し、まず『セッション』を先に製作しました。『セッション』の成功が、『ラ・ラ・ランド』の実現に繋がったのです。
02|インディーズ映画として始まった企画
当初『ラ・ラ・ランド』は低予算のインディペンデント映画として構想されており、チャゼル監督は長らく出資者を探して奔走していました。ハリウッドでミュージカルは商業的に難しいという認識が強く、なかなか出資が集まらなかったのです。『セッション』の評価が一気に追い風となり、ライオンズゲートが正式に製作を支援することで、ようやく企画が本格化しました。
03|オープニングの高速道路シーンはロサンゼルス愛の象徴
冒頭の「Another Day of Sun」が歌われる高速道路上のシーンは、ロサンゼルスの象徴的な景観である110号線の合流点で撮影されました。撮影は酷暑のなか、車100台と150人以上のダンサーを用いて2日間かけて実施。ロスの喧騒の中にも夢とエネルギーが溢れていることを、あの一場面で表現しています。
04|35mmフィルム撮影にこだわった理由
本作はデジタルではなく、あえて35mmフィルムで撮影されました。チャゼル監督は、往年のミュージカル映画が持っていた独特の質感を再現するため、アナログにこだわったのです。さらに色味も1950〜60年代のテクニカラー作品を意識し、現代の映画とは一線を画すビジュアルが実現されています。
05|資金難でパリの撮影が断念された
ラストの「もし別の未来があったら…」という幻想シーンの一部には、当初パリの景観を使用する案もありましたが、予算の都合で実現しませんでした。結果的に、ロサンゼルスのスタジオセット内での撮影に切り替えられたものの、逆に「映画的な夢の世界」を象徴する空間演出として高く評価されています。
🧍キャストと演技にまつわるトリビア
06|主演候補はマイルズ・テラーとエマ・ワトソンだった
当初、セバスチャン役にはマイルズ・テラー、ミア役にはエマ・ワトソンがキャスティングされていました。ところがスケジュールや契約条件の折り合いがつかず、最終的にライアン・ゴズリングとエマ・ストーンが主演に決定。結果的に、このペアが奇跡的な化学反応を生みました。
07|エマ・ストーンは実際にオーディションを受けていた
劇中でミアが何度もオーディションを受けるシーンは、エマ・ストーン本人の実体験が元になっています。彼女もブロードウェイでの失敗や、数え切れない落選経験があり、そのリアリティが画面からも伝わってきます。特に「The Fools Who Dream」の独唱シーンでは、涙ながらに語る演技が絶賛されました。
08|ライアン・ゴズリングは3ヶ月でジャズピアノを習得
セバスチャン役のライアン・ゴズリングは、吹き替えなしでピアノ演奏を披露しています。彼は役作りのためにプロのジャズミュージシャンに師事し、3ヶ月間、1日4時間以上の練習を積んだといいます。特に印象的な「City of Stars」の演奏は、撮影当日に一発撮りされたそうです。
09|ダンスシーンは深夜に1テイク勝負で撮影された
「A Lovely Night」のダンスシーンは、魔法のような黄昏の空が背景となっていますが、実は“マジックアワー”の数分しか撮影時間がなく、テイクは数回しか撮れなかったそうです。完璧なカメラワークと演技、振り付けを合わせる必要があり、まさに奇跡的なワンシーンとなりました。
10|監督は俳優の疲労感も意図して演技に取り入れた
チャゼル監督は、ダンスや演奏シーンであえて何度もリハーサルと本番を重ね、俳優たちに“本物の疲労感”が出るまで撮影を行いました。これはミュージカル映画でありながら、登場人物の「現実の生活感」を滲ませる演出の一環です。
🎥演出と世界観のトリビア
11|4つの季節で物語が区切られている
『ラ・ラ・ランド』は「冬」から始まり「冬」に戻る四季構成で展開されています。これは物語の巡回性を象徴しており、二人の関係が時間の中で変化していく様子を季節と重ねて表現しています。特に最後の「冬」は、現実と“もう一つの未来”の対比を強調する鍵となっています。
12|ドリームシークエンスは絵画的に設計された
ラスト10分に描かれる“夢のような別の人生”のシークエンスは、色彩と構図が極めて緻密に設計されており、まるで美術館のような印象を与えます。このパートはミュージカル映画『シェルブールの雨傘』へのオマージュでもあり、失われたロマンスを芸術的に昇華した演出が光ります。
13|ジャズクラブの名前「Seb’s」に込められた意味
セバスチャンが開いたジャズクラブ「Seb’s」は、彼の個人性だけでなく“Self Expression and Beauty(自己表現と美)”というメッセージの頭文字とも解釈できます。夢を貫いた彼の生き様そのものを象徴しており、ミアが店の名前を見て涙するラストはその想いを深く物語っています。
14|色彩設計はキャラクターの心情に連動している
ミアが着るドレスの色はシーンごとに異なりますが、これには彼女の感情や状況を反映する意図があります。青=希望、赤=情熱、黄=高揚、緑=変化、といった色彩心理学が画面に込められており、無意識に観客に印象づける効果を果たしています。
15|オールドハリウッドの再現が随所に
映画全体を通して、『雨に唄えば』『バンド・ワゴン』『王様と私』など、往年のミュージカル映画へのオマージュが散りばめられています。背景セット、照明の当て方、ダンスシーンのカメラアングルまでがクラシックを意識しており、現代の観客にも“古き良き映画”への敬意を伝えています。
(続きます:次の投稿で最後の10項目+まとめ・SEO情報を出力します)
続きです。以下で『ラ・ラ・ランド』のトリビア記事を完結させます。
🎞️映像・音楽・細部に込められた工夫
16|主題歌「City of Stars」は当初デュエットではなかった
アカデミー歌曲賞を受賞した「City of Stars」は、もともとライアン・ゴズリング単独のソロ曲として作られていました。しかし、監督と音楽チームの提案により、ミアとのデュエットにアレンジされたことで、二人の関係性や感情の交差がより強く表現される楽曲に生まれ変わりました。
17|作曲家ジャスティン・ハーウィッツとの長年の協力関係
音楽を担当したジャスティン・ハーウィッツは、デイミアン・チャゼル監督の大学時代からの友人です。『セッション』『ラ・ラ・ランド』『バビロン』と続くコンビは、映像と音楽を完全に同期させた作品世界を生み出し、映画音楽の新たなスタンダードを築いています。
18|照明もミュージカル的に演出されている
特にプラネタリウムでの浮遊シーンなどでは、物理的リアリズムを超えた「舞台的」な照明演出が意図的に取り入れられています。現実と幻想を曖昧に繋ぐ役割として、照明の色・強度・方向性が非常に精巧に設計されています。
19|小道具にも仕掛けられた音楽的モチーフ
セバスチャンのピアノやクラブの看板などには、実際にジャズ史上重要な音楽的モチーフが含まれています。中でも“ジャズの伝統”と“個人の夢”という二つのテーマを象徴する楽器の配置や照明が、物語の文脈とリンクしています。
20|衣装デザインは時代を超える普遍性を目指した
衣装デザイナーのメアリー・ゾフレスは、「今」のファッションではなく、「古き良き時代」を感じさせる普遍的なスタイルを採用しました。ミアのカラードレスやセバスチャンのクラシックなスーツなど、時代を超えても色褪せない“映画的美学”が全体を貫いています。
🔍テーマと解釈に関するトリビア
21|「夢」と「愛」は両立しないのかという問い
『ラ・ラ・ランド』の最大のテーマは、“夢”と“愛”の選択です。ミアとセバスチャンが互いの夢を応援しながらも、最後には別々の道を選ぶ展開は、ロマンチックであると同時に現実的な決断を映し出しています。そのリアリズムが、多くの観客の心に残る所以です。
22|“もしも”のラストがもたらす二重の感情
終盤の幻想シーンは、観客に「もしあのとき違う選択をしていたら…」という余韻を残します。これはチャゼル監督が意図した“夢と現実の交錯”であり、物語をハッピーエンドにもビターエンドにも見せる巧妙な語りの構造になっています。
23|現代の“自己実現の代償”を映し出す物語
本作は、単なる恋愛ミュージカルではなく、現代社会における“自己実現”の難しさを描いた作品でもあります。夢を叶えるためには、何かを犠牲にしなければならない現実と、それでも追いかけずにはいられない衝動が、ミアとセバスチャンの姿に重ねられています。
24|ミュージカルという形式の再定義
クラシックなミュージカルの形式を踏襲しながらも、本作は“日常と非日常の交差”を大胆に描いています。ダンスや歌が突然始まることへの違和感を、幻想として処理する手法が取り入れられ、観客に新しいミュージカル体験を提示しています。
25|観客に「自分の物語」を重ねさせる構造
『ラ・ラ・ランド』が世界中で支持されたのは、ミアとセバスチャンの物語が“個人の夢と現実の葛藤”として普遍的であるからです。観客自身が自分の経験を彼らに重ね、人生の選択や後悔を回想できるような構造になっているのが、本作の大きな強みです。
📝まとめ
『ラ・ラ・ランド』は、夢を追い続ける美しさと、現実がもたらす切なさを同時に描いた稀有な作品です。
斬新な演出や音楽の力だけでなく、登場人物たちの内面や選択にも深い人間ドラマが宿っています。
こうした25のトリビアを知った上で観直すことで、新たな発見や感情が湧き上がるはずです。あなたもぜひ、“もう一つのエンディング”を心に描きながら、あの色彩の世界へ再び足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。