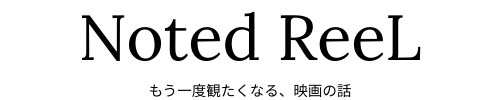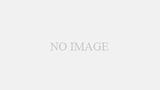2018年、サンダンス映画祭で衝撃的なデビューを飾ったアリ・アスター監督の『ヘレディタリー/継承』。
家族に潜む“呪い”と“継承”を描いた本作は、A24の代表作としてホラー映画の新たな金字塔となりました。
この記事では、その制作秘話からキャストの裏話、演出のこだわり、恐怖の根底にあるテーマ性まで、25のトリビアを通して『ヘレディタリー/継承』の恐ろしくも魅惑的な世界を深掘りしていきます。
🎬制作と構想にまつわるトリビア
01|監督の“喪失”体験が物語の出発点だった
アリ・アスターは、個人的な喪失体験や家族との確執を昇華する形で脚本を構想しました。当初は「家族ドラマ」として始まった本作ですが、次第にそれが恐怖と不安に満ちた“儀式的ホラー”へと変貌していきます。ジャンルとしてホラーを選んだのは、感情の極限状態を描くには最もふさわしいと考えたためだと語られています。
02|原案タイトルは『The Mourning Family』だった
『Hereditary』というタイトルが最終的に採用される前、本作は『The Mourning Family(喪に服す家族)』という仮タイトルで脚本が書かれていました。家族が直面する死と喪失を核とした物語であることから、心理劇としての側面が強調されていたことがうかがえます。
03|制作決定の鍵は「ラスト30分の衝撃」
A24のプロデューサー陣が脚本を一読して即決した要因の一つが、第三幕に突入するラスト30分の構成でした。緻密な伏線と演出の集積による“悪夢的な加速感”に、スタジオはこれを単なるホラーではないと判断したとされています。
04|初監督作とは思えない構成力
本作はアリ・アスターの長編監督デビュー作ですが、緻密なプロット、演出のコントロール、構図の選定など、まるでベテランのような手腕を発揮しています。大学で映画理論を学び、短編で数々の異常心理を描いてきたバックグラウンドが、すでに確かな演出力を育んでいました。
05|意図的に“説明不足”にした構成
『ヘレディタリー』は、多くの謎や設定があえて明確に語られません。観客の“想像力”と“解釈”を刺激するため、背景説明や世界設定の多くはビジュアルや小道具に委ねられています。監督は「分かりすぎる恐怖よりも、理解しきれない不安のほうが深く残る」と語っています。
🧍キャストと演技にまつわるトリビア
06|トニ・コレットは最初オファーを断っていた
主演のトニ・コレットは、当初「ホラーには出演しない」と断っていました。しかし脚本を読んだ後、その深いドラマ性とキャラクターの内面描写に惹かれ、出演を即決したといいます。実際、彼女の演技は批評家から「キャリア最高」とも評されました。
07|アレックス・ウルフは精神的後遺症に悩んだ
息子ピーターを演じたアレックス・ウルフは、役作りの過程で心身に強いストレスを受けたと後に告白しています。特に“ある衝撃的な事故”のシーンは、撮影後もしばらく悪夢にうなされるほどの精神的負荷があったそうです。
08|“首を切られた演技”にリアルな工夫
チャーリーを演じたミリー・シャピロは、ホラー特有の「異物感」を巧みに演出しました。特に彼女が発する“舌を鳴らす音”は、観客のトラウマになるほど印象的。この音はアドリブではなく、監督が脚本の段階から意図的に設計していた演出要素でした。
09|俳優たちに“家族として過ごす時間”を設けた
撮影前にキャストたちに一週間のリハーサル期間を与え、「家族として過ごす」ことが求められました。これは即興的な反応やリアルな親子関係を作るためで、特に母と息子の口論シーンにはその効果が色濃く表れています。
10|祖母役エレン・テーパーは“存在感”で選ばれた
祖母エレン役のキャスティングは、“登場しない人物”の印象を強く残すという難題でした。そのため、彼女の写真の表情や葬儀シーンでの存在感に最大限の注意が払われました。わずかな登場にもかかわらず、物語の中で“最大の影響力”を持つ人物となっています。
🎥呪いや血統にまつわる演出のトリビア
11|家の構造は“ドールハウス”そのものだった
映画全編で登場する家のセットは、実際に「巨大なドールハウス」のように設計されています。これは主人公アニーの職業(ミニチュアアーティスト)ともリンクし、登場人物たちが“誰かの意志によって動かされている”ことを象徴しています。
12|“首”にまつわる描写が全編に仕込まれている
本作では“首”という身体部位が繰り返し象徴的に登場します。絵画や模型、小道具の配置に至るまで、細部に“切断”や“ねじれ”の暗喩が散りばめられており、後半の展開を不気味に予感させます。
13|悪魔パイモンの儀式的設定は実在の文献が元に
映画に登場する“パイモン”は、実際に17世紀の魔術書『ゴエティア』に登場する悪魔に基づいています。王の一柱とされ、富と知識をもたらすとされるこの存在は、儀式や象徴、シンボルまで文献の記述を忠実に参照しています。
14|ラストシーンは“宗教的アート”を意識した構図
物語の終盤、ツリーハウスでの儀式シーンは、古典宗教画のような構図で描かれています。神像、崇拝者、玉座などが“逆の神性”を表現しており、観客に不穏で歪んだ神聖さを印象づけます。
15|“継承”は呪いと役割のダブルミーニング
タイトルの“Hereditary”は「遺伝的な」という意味ですが、映画では単なる血の継承にとどまらず、“呪い”と“運命”が子から子へと引き継がれる様を描いています。そこには“自分ではどうにもできない力”に抗えない悲劇が色濃く表れています。
🎞️映像・音楽・細部に込められた工夫
16|すべてのセットは“解体可能”だった
本作の撮影では、特撮や合成ではなく“物理的に分解可能な家のセット”が用意されました。これにより天井を取り外し、異常なカメラアングルやドローン的な視点が可能に。閉塞感の中に“見られている感覚”を演出する工夫が施されています。
17|音楽は“音”より“空気の圧”を重視
音楽を担当したコリン・ステットソンは、ホラー映画らしい旋律を避け、不快で不穏な空気感を強調する音づくりを行いました。特に弦楽器や金属音の加工により、観客が無意識に不安になる“音圧”を生み出しています。
18|舌打ち音は“サウンドデザインの核”だった
チャーリーの“カチッ”という舌打ちは、全編を通じてサウンド面でも強調されています。編集段階でその音を空間に響かせたり、場面の繋ぎに使うことで“死者の存在”を暗示する重要な効果音として機能しています。
19|点灯と消灯のタイミングが“演出装置”に
本作では照明のオン・オフが単なる場面転換でなく、“次の段階へのシグナル”として使われています。特に祖母の部屋の明かりや、ツリーハウスの光の使い方は、不可視の存在の干渉を示す演出装置となっています。
20|エンドクレジットの“沈黙”に宿る余韻
映画が終わった後、エンドクレジットはほぼ無音で始まります。これは観客が物語の恐怖を咀嚼する時間を確保するための演出意図であり、また“すべてが終わったわけではない”という感覚を与える効果を持っています。
🔍テーマと解釈に関するトリビア
21|“家族”という逃れられない牢獄
『ヘレディタリー』は、ホラーでありながら、家族という制度そのものを恐怖の源にしています。愛する人であっても、それが原因で人生が破壊されていくという構造は、“共依存”や“遺伝的宿命”の問題と深く結びついています。
22|監督は“悲劇としてのホラー”を目指した
アリ・アスターは本作を「悲劇をホラーの形式で語った作品」と定義しています。観客が恐怖で叫ぶのではなく、悲しみで沈黙するような映画を目指し、物語の中心にあるのは“喪失”と“罪悪感”です。
23|登場人物の選択はすべて“操られている”
物語の中盤以降、登場人物たちが選ぶ行動の多くが、実は事前に仕組まれた導線であることが明らかになります。“自由意志が奪われる恐怖”は、カルト的組織や支配構造への批判とも読み取ることができます。
24|精神疾患とオカルトの二重解釈
本作の最大の仕掛けの一つは、「すべてが超自然ではなく、精神疾患による幻覚だった可能性」も残している点です。アニーの母が精神的に不安定だった過去と、家族の奇行は、“遺伝”のテーマと巧みに絡み合います。
25|“継承”とは“アイデンティティの消失”でもある
最終的にピーターは“自分ではない何か”に変貌します。これは「子が親から継ぐもの=望まぬ役割やカルマ」として解釈できます。個人が個人でなくなる瞬間、そこにはホラー以上の哲学的恐怖が潜んでいるのです。
🧠まとめ
『ヘレディタリー/継承』は、家族という最も身近な絆に潜む“逃れられない呪い”を描き切った、現代ホラーの傑作です。
不快なまでにリアルな人間描写、細部まで仕込まれた象徴性、そして衝撃のラストまで、全体が一つの“儀式”として機能しています。
こうしたトリビアを知ることで、本作が単なるホラー映画ではなく、観るたびに意味が変わる“考察型映画”であることが実感できるはず。
あなたもぜひもう一度、祖母の影が落ちる家で、その“継承”を見届けてみては?